
ディープなやきもの。Vol.2 釉薬 ~自然から生まれた釉~
特定の世界では常識的なこと、知らなくても困らないけれど知っていたらちょっとツウ(!?)なこと。
窯業界で数多く存在する「ディープなやきもの」情報を何度かに分けてお届けしていきます。
第2回目は『釉薬』について。釉薬ができた歴史などについてクイズを挟みながらご紹介します。どんどんマニアックになっていきますが、ぜひ、クイズに挑戦しながら読み進めてみてくださいね。
取材協力:長崎県窯業試験センター
釉薬の始まり

日本では、土から容器を作る「土器」から焼きものづくりが始まりました。次第に窯を築く技術ができていくと、土器よりも高い温度で焼成される、頑丈な器(=陶器)を作る技術も培われていきました。
あるとき、窯の中の温度を高めるために、薪を大量にくべた際、燃えた灰がたまたま生地に付着して反応がおこり、焼いた器に透明なガラス質の光沢ができました。
この自然現象を人工的に作りだしたのが、「釉薬」です。

このころの釉薬には、土灰釉(どばいゆう)、柞灰釉(いすばいゆう)、藁灰釉(わらばいゆう)など、様々な灰で人工的に試した釉薬が存在しました。
・柞灰(いすばい)
柞(イスノキ)を焼いて製していたもの。やわらかな色合いとしっとりした釉肌が特徴。
・土灰(どばい)
木の枝や落ち葉などの雑木を燃やした灰から作られる。金属が含まれていないので淡い色合いになる。
・藁灰(わらばい)
稲を乾燥させたわらを燃やしたあとの灰を使った釉薬。酸化焼成をすると白く乳濁した色合いになるため全体に掛けるのではなく、雪がかかったように掛けわけるのが特徴。
この3つの灰は基礎的な釉薬です。この基礎釉に色を付けていくと器全体に色がつきます。
進化していく釉薬
現在の基礎的な釉薬(=基礎釉)は、透明釉(とうめいゆう)、マット釉、乳濁釉(にゅうだくゆう)の3種類です。それぞれ器の雰囲気や質感を変えるために釉薬をかけ分けています。



鉄、銅、コバルトの3種類の鉱物はそれぞれ発色が違います。また、空気を十分に含ませて焼く酸化焼成と、空気を途中で止めて焼く還元焼成があり、この焼成方法によっても色が変化するのでレパートリーは多くあります。
鉄
還元焼成の場合:

酸化焼成の場合:


銅
還元焼成の場合:
酸化焼成の場合:

コバルト
酸化還元ともに:

現在は技術が進歩したことにより顔料を使用し色も増えてきました。
しかし顔料は、色が粒状になっているので、ペンキのようにべたっとした色になります。
一方で、鉱物の場合は、釉薬に溶け込むので透明感があり、ステンドグラスのように発色します。この性質の違いから、思うように発色しない場合も多くあります。
初めは自然現象でできた釉薬ですが、現在では様々なバリエーションの釉薬を作ることができます。同じ釉薬をかけても窯の中での場所や、生地の状態によっても色むらや焦げが出てきてしまうこともあります。
窯元ではそれをなるべく出さないように日々研究をしていますが、窯の中のことも自然現象が多くあるので、まったく同じ器を完璧に作る事はできません。
波佐見焼だけではなく、焼き物全体にそういった性質があります。成形方法や材料によって多種多様な器がありますので、お手元に届いた器や自分で選んだ器を見比べてみるのも面白いですよ。

▶︎『ディープなやきもの。Vol.1 ~パット印刷~』から読む。
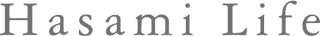
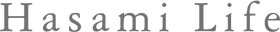
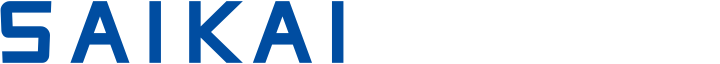
コメントを残す