
窯元の火を止めるな! 技術と雇用をつなぐ、波佐見焼企業のM&Aに迫ります。
長年、分業でものづくりを続けてきた波佐見町。
陶土屋、型屋、生地屋、窯元、商社。さらに言えば、それらの現場を支える絵筆職人、ハンコ屋、カンナ屋などなど…。
多くの人の手をわたって波佐見焼がつくられていく様子は、これまでもHasami Lifeで紹介してきました。
そのおかげで量産ができたり、職人さんそれぞれの得意を掛け合わせたバリエーション豊かな器がつくれたり。分業であることは、産地としての波佐見のアイデンティティのひとつと言えると思います。
ただ、時代が移れば社会も市場も変わり、産業のあり方にも変化が求められます。産地として培ってきた強みは活かしつつ、当たり前に続いてきた分業体制を見直すことも、ときに必要なのかもしれません。
2021年12月、波佐見町で4代にわたって器を焼いてきた窯元の高山陶器(現・株式会社高山)が、商社である西海陶器株式会社に事業承継をおこないました。波佐見焼に関わる企業のM&A(=Mergers 合併 and Acquisitions 買収)は、とても珍しいことなのだそうです。
後継者不在を理由に事業をたたむケースも増えているなかで、両社はどうやって事業承継に結びついたのか。その先にどんな未来を見据えているのか。
高山の4代目である高塚英治さん、事業承継後に高山の代表取締役を務めている小林善輝さんという、新旧の社長に話を聞きました。
高山のこれまでとこれからを知ることで、波佐見焼の未来へのヒントが見えてくるかもしれません。
なんとしても継承したいものがあった
波佐見町の中心から、お隣の嬉野市へと抜ける道の途中。
小さな橋をわたると、大小の建物と立派な煙突が見えてくる。煙突には「高山」の文字。
株式会社高山はこの場所で、およそ90年前に高塚製陶としてその歴史をスタートした。
迎えてくれたのは、前社長の高塚英治さん。今年の8月にオープンしたばかりの新工場の一角で話を聞いた。

「高塚家のルーツは和歌山なんですね。長崎には蘭学の勉強に来たか、勉強に来る人を連れてきたか、定かじゃないんですけども、その関係で来て。祖父母が創業者で、父、おじ、そしてわたしで4代目です。おじいさんは中尾山、おばあさんは三股(みつのまた)っていう、いずれも波佐見の焼きもののはじまりの地で生まれ育っています。
この場所に来る前、祖父母は長崎街道の塩田宿(現在の嬉野市塩田町)で生地職人をしていたそうです。そこに行ったのはなんでかっていうと、駆け落ち(笑)。お互いの両親に反対され、塩田に駆け落ちして。ふたりともある程度技術が上がって飯を食えるようになってから、許しも得て、こっちに戻ってきた」
そのタイミングで、生地職人から窯元へ転身。
登り窯を借りてコツコツ焼きものを焼くと、少しずつ商売が軌道に乗って生産量も増えていく。やがて広い土地が必要になり、昭和8年に現在の場所(波佐見町小樽郷)へと移ってきたそう。

――:立派な煙突がシンボルのようにそびえ立っていますが、今はてっぺんに植物が生えていますね。
いつごろまで現役で稼働していたんですか?
「知ってる限りで、中学生のときには(植物が)生えてたね。だからもう50年ぐらい前になるかな」
――:それ以降は別の窯で焼いていた?
「トンネル窯でね。ふつう窯の寿命っていうのは、だいたい20〜30年。これは盆正月も火を止めちゃいけないんですよ。八幡の溶鉱炉と一緒で、ずっと焚きっぱなし。火を止めたら縮んで、くしゃっと潰れちゃう。
昔はそれでも経営が成り立つくらい売れてたってことだ。商品が足りなかったんですから。焼き上がった器の出口で、商社の人が順番待ち。検品もするかしないかのような感じで、商品をトラックに入れていく。そういう時代もあったんですよ」
器が飛ぶように売れる時代はよかった。
けれど、高度経済成長期を過ぎ、バブルがはじけて、不景気に突入することは目に見えていた。器も次第に売れなくなっていく。
そこで20年前には、窯の天井部のレンガをすべて外し、火を止めても崩れないように工事をした。
おじさんの急逝を機に、42歳で家業を継いだ高塚さん。さまざまな荒波に揉まれながらも、歴史ある窯を続けるために奮闘してきたことが伝わってくる。

そんな高山が次に直面した課題が、後継者の不在。
覚悟を持ってあとを継ぐ人がいなければ、ものづくりの火はやがて途絶えてしまう。
「すごい苦悩しましたよ。親の苦労も知ってるし、働いてきてくれた地域のお母さんたちのことも知っている。経営的にも厳しくなってきたなかで、どうしたらこの事業を残せるだろうかって」
そんなとき、頭に浮かんだのが、西海陶器会長の児玉盛介さんだった。
「会長とは10年以上の付き合いで。『これからは商社もつくり手も一緒になって、地域の観光を巻き込みながらやっていかないと生き残れないぞ』っていうことは、ずっと聞かされてたんです」
この人になら託せる。
そんな想いを胸に事業承継の相談に行くと、児玉さんからはふたつ返事でOKがかえってきた。
――:でも、葛藤はなかったですか。事業承継をするということは、代々家業として続いてきたものを、手放す感覚にもなりそうな気がします。
「うちの技術と社員の雇用をつないでいくには、これが一番ベストかなって。とくにパッド印刷に関しては、20年間で全国有数のレベルまで駆け上がりました。それはやっぱり、なんとしても継承したかった」

つきたてのお餅のようなシリコンパッドにインクをつけ、スタンプの要領で絵付けをしていくパッド印刷。
機械で次々に絵付けしていく様子は、素人が見ても、どこに差が出るのかよくわからない。
「よく言うのは、機織り機はどこにでもあるんです。その機織り機をどう扱うかによって品質の違いが生まれる。うちはその小さな差別化を20年間ずっとやってきました。開発してばかりで、あんまりお金にはならなかったんだけども(笑)。日本の大手のメーカーさんもうちの技術は認めてくれているし、それが今回のM&Aにもつながったと思っています。
西海さんは西海さんで、商社としての蓄積されたノウハウがあるしね。海外に向けた新商品の開発もやっていきたい。結果的には、とっても前向きな決断なんです」

「それとね、昔から彼と一緒に商売をやりたかったんですよ」
そう言って指し示す先には、事業承継に伴って新社長となった小林善輝さんの姿がある。西海陶器の常務取締役として、波佐見焼”ブランドの立ち上げに貢献してきた立役者のひとりだ。
地域のなかに、生活できる人をいかにつくっていくか

まったくの未経験から独学で、西海陶器の会計システムを構築したり。グリーンクラフトツーリズム研究会というNPO法人を立ち上げ、産地の特性を活かした観光商品やプロジェクトを企画・運営したり。
それまで波佐見になかった仕組みや価値観を持ち込んできた小林さん。
今回のM&Aも、産地としての新しい一歩にしていきたいと考えている。
「情報発信や観光の体験づくりって、西海陶器のような商社単独でしても、それほどインパクトはないんです。メーカー自ら、想いやつくり方を発信することで生まれる説得力がある。今はこの場所を起点にしたツアーや体験の事業計画を立てています」
たとえば新工場は、観光で訪れた人たちが見学しやすいようにレイアウトを組んでいる。
ペーパーレス化も進め、各現場に設置したタブレットで生産を管理。スマートフォンでQRコードを読み取ることで、作業工程の解説が受けられるような展示も考えているのだとか。

敷地内にはほかにも、レストランや宿泊施設、ショップや窯の排熱を活かしたハウス栽培の農園、ドッグランなどもつくる予定。
また、新工場のオープンに伴って空いた旧工場には、「聖栄陶器」という別の窯元が移転してくる。「西の原」に次ぐ、波佐見の新たな観光拠点をつくっていきたいという。
さらには、人材育成の構想もある。
「波佐見が高度成長期に発展していったのは、メーカーが生地屋さんを育成したから。メーカーの生産体制のなかに入って、生地をつくれるようになって独立していった。本来メーカーは、産業の裾野を広げる役割を持っていました」
独立する際には機械を譲り渡したり、独立してしばらくのあいだはものづくりだけに専念できるよう、陶土の代金を肩代わりするような慣習があったり。
先輩のつくり手が、次世代のつくり手を育て、送り出す文化が波佐見にはあった。
その役割を復活させるためにも、高山ではこれから、敷地内に訓練校のような施設をつくるそう。
「要するに、自立できる人を育てる会社風土にしたいんですよね。今、生地屋さんが減っているっていう課題も、ここから解決していけるだろうと」

中国の大工場などでは、機械による自動生産がどんどん進んでいる。
その先に待っているのは、資本力がものを言う世界。そこで働く人の仕事も、ロボットの手助けの一部でしかなくなる。
人手不足の問題は解消されるかもしれない。けれど、そうしてつくったものも、果たして波佐見焼と呼んでいいのだろうか?
「値段だけのモノ売りの世界に入り込ませちゃいけない」と、小林さんは言う。
「地場産業にとって大事なのは、地域のなかに、生活できる人をいかにつくっていくか。所得を上げて、働く人を増やして、地域に産業を残していかないといけない。そのためには、機械でできない部分の価値をもっとつくっていく必要があるだろうと思うんです。
ここを事業承継するときに、(児玉)会長からは『働きたい場所をつくれよ』と言われています。それ以外は好きにしてくれていいって」
一時は20名を切っていた高山のスタッフ。
事業承継後、SNSでの発信などにも力を入れてきたことで、今では30名の規模に。県外からの応募や問い合わせも増えている。

M&Aを通じて、さまざまな変化が生まれつつある高山。
取材時は新工場に移転したばかりのタイミング。事務所の机や備品が足りていなかったり、ショップは改装中だったり。以前から働いていたスタッフのみなさんも、新しい環境に馴染んでいく過渡期のように感じられました。
このエリアが完成したときにまた取材したいです、と伝えると、小林さんからはこんな言葉がかえってきました。
「完成せんちゃない? 少なくとも、会長かわたしが倒れるまでは(笑)」
一度は途絶えかけた火も、まだまだ灯し続けることができる。そんな産地のモデルケースがここから生まれていくのかもしれません。
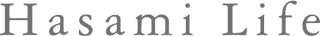
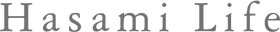
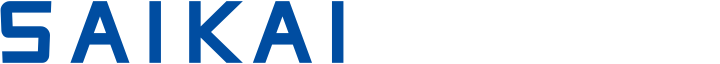
コメントを残す