消えゆく職人技、わら包装の美しさ。
波佐見町では、400年以上前から焼きものの技術が連綿と受け継がれてきました。しかしその一方で、絶えようとしている技術もあります。それが「わら」を使った包装です。
使う素材は、わらと、わら縄。それのみで割れるおそれのある焼きものを運んできました。わら包装を見たことのない世代にとっては、まったく未知の技術ですが、昭和40年代ごろまで、わら包装は一般的だったといいます。
江戸時代から日本全国に日常使いできる焼きものを届けてきた波佐見。大量の器を運び出すのは大変なことだったでしょう。
焼きものが昔はどんな風に包装されていたのか、気になりませんか。今回、わら包装の経験がある土橋誠さんにお話をうかがいました。
手が覚えている、わら包装の仕方。
土橋さんにわら包装の取材をお願いすると「じゃあ準備しとくけん」とのこと。どんな準備が必要なのかたずねると、前日に一部のわらをやわらかくするために濡らしておく必要があると教えてくれました。そうした下準備がいるのだと知って、ますます興味が深まります。
取材当日、家にお邪魔すると、広々とした納屋へ案内されました。
最初のステップは、わらの準備。
前日に濡らしておいたわらを、まるで長い髪の毛をとかすように、指を通して梳(す)いていきます。
梳(す)かれたわらは、まっすぐ長いわらと、鳥の巣のような短いわらに分けられます。この二種類のわらをそれぞれひもと緩衝材として用いて、包装していきます。ひとつの素材を余すことなく使い切る先人の知恵ですね。
わらの準備ができたら、包装していきます。作業はざっくりいうと、3つのステップに分けられます。
【わら包装の3ステップ】
- 輪をつくる
- すからげをつくる
- 外包装をする
これで完成!……とのことですが、輪? すからげ? まったくイメージが湧きません。
「まあ、見てればわかるさ」と土橋さんはどんどん手を動かしていきます。
まずはステップ①、輪づくりです。
まっすぐ長いわらをねじってから円をつくり芯にし、その上から押さえつけるように濡らしたわらを巻きつけていきます。この巻きつける部分にはしなやかなわらが必要になるため、前日から濡らしておいたのだそうです。
「ぶつかったときに割れやすい焼きものの上下の縁を、この輪が守ってくれるのよ。包み方によっては、取っ手にもなるけんね」
輪の大きさは、器よりも少し大きいくらい。器のサイズを細かく測ることなく、目測であっという間に輪をつくっていく土橋さん。最後に、はみ出したわらを丁寧に包丁で切り落としていきます。
「昔は荷包丁っていう、わら包装する専用のもっと大きな包丁があったとけど、もうなくなったもんね。切れ味のいい、松原包丁を使っとったとよ。今私が使ってるのも、松原のもの。すごく切れ味がいいから、砥石を使って研いで、長いこと使っとるよ」
松原包丁は長崎県の大村市でつくられ、県指定伝統的工芸品にも指定されています。昔から波佐見町でも愛用されていたようです。
「次は『すからげ』をつくるからね」
ステップ②のすからげ。聞き馴染みのない言葉ですが、内包装のことをこう呼びます。今回このすからげで包む器の枚数は10枚。ふたつのすからげをひとつにまとめて、一度に20枚を包装します。器の大きさによって、すからげに何枚包むのかもある程度決まっていたそうです。
まっすぐ長いわらで外側を、鳥の巣のような短いわらで器のあいだを保護して、包んでいきます。
包んだものをわら縄で縛れば、すからげの完成です。今回、わらはすべて土橋さんの田んぼのものを使用していますが、わら縄だけは購入したものを使用しました。土橋さんがわら包装をしていたころには、わら縄をつくる職人さんが町内にいて、その人たちから購入していたとのことです。
もうひとつ、すからげをつくって、2つのすからげを輪ではさみ一緒に縛ります。
もうしっかり包んであるように見えるのですが、さらに側面に長いわらを重ねて巻いていきます。これがステップ③、外包装です。

巻いて縛りあげたら、外側のはみ出したわらを松原包丁でカット。さらにひもで縛りあげて、ようやく完成です。
72歳になっても衰えていない見事な腕前。もうわら包装をしていたのはずいぶん昔のこととうかがっていたのですが、「手が覚えとるけんね」と迷いなく手を動かす姿はまさに職人でした。
わら包装には、いろんな包み方があるそうです。焼きものの大きさや枚数によって異なると、もうひとつの包装もつくって見せてくれました。
美しく儚い、わら包装の今。
わら包装をした焼きものは、どんな風に届けられたのでしょう。
「だいたい、汽車で届けてたとよ。当時こうした形で巻いてあるものは焼きものって認識されてたから、『これはワレモノだ』と丁寧に扱ってもらってたんじゃないかな。焼きものだからね、どうしても輸送中に割れてしまうこともあったけど、でもわらで巻いたら滅多なことでは割れなかったとよ」
機能性があって、見た目も美しく、自然にもやさしい、わら包装。受け継いできた人たちの美意識を感じさせます。それでも、時代の流れの中で、少しずつ消えていきました。
なぜなら、わら包装は職人技だったから。焼きものを大量に流通させるために、誰にでも簡単にできる箱での包装に変わっていく必要があったのです。
「やっぱり、紙やダンボールで包む方が早かけんね。私が商社に入社したときはもうすでに、すべてがわら包装じゃなかったとよ。大きなお皿や火鉢とかはわらで巻いて、急須や茶碗とか小さいものは箱に入れてたけんね。そうやって、だんだんわら包装はなくなっていったもんねぇ」
土橋さんが若いころにはまだ、荷造りをしていた商社には少なくともひとりずつはわら包装ができる職人さんがいたそうです。けれど、現在ではこの技術を持つ人は、土橋さんが知る限りでは波佐見町で2、3人ほど。取材時に72歳の土橋さんより歳下でわら包装ができる人は、もういないだろうとのことでした。
そもそも、わら自体も現在では入手しにくいそうです。
「昔は農家さんから、わらを買ってたと。最近は、それも難しいけんね。どこもコンバインっていう機械で稲刈りするとよ。そうすると、刈りとるときに細かく裁断されるもんね。肥料にして活用しとるけど、包装したり細工したりする材料としては細かすぎて使えない。バインダーと呼ばれる機械で長い穂のまま刈って、天日干しして……って手間をかけとるもんじゃないと、この長さにはならないからね」

焼きものは高温で焼いているため、土に還ることがありません。今でも、昔の登り窯の近くでは江戸時代などの焼きものが発掘調査で出土していますが、わら包装は各地に輸送され到着すれば役割を終えるため、後世に残ることはありません。
つまり、端正で美しいわら包装を見ることは、そのうちできなくなるのです。
惜しいことですね、とこぼすと、土橋さんは明るく笑ってこう言ってくれました。
「また必要になったら、私がつくるけん。いつでも頼んでよかよ」
できることなら、わら包装を知らない人たちにこの技術を知って、実物を見てほしいです。「将来、日本各地で行われている焼きものの展示会や波佐見町のお祭りなどで、土橋さんによるわら包装を広めることができないだろうか」と今回の取材を通して考えました。
消えゆく職人技を、せめて人々の記憶に美しく残していけたらうれしいです。
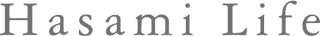
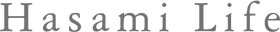














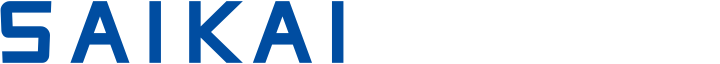
コメントを残す