
THE HASAMI-YAKI vol.6
色の魔法をかける、釉薬の不思議
釉薬(ゆうやく、うわぐすり)。それは、焼きものの第一印象を決める「色」を生み出す魔法の液体。器を選ぶときは、形だけでなく、色を重視しませんか? 買い手はもちろん、作り手も大きくこだわる色。その秘密は釉薬にあり! 今回は、波佐見焼の色を専門分野とするふたつの職業を紹介します。
※内容を一部加筆し、更新しました。
意外と知られていない「釉薬屋」の仕事
はじめに訪れたのは、『窯研株式会社』。釉薬と焼きもの用の絵の具を扱う会社、いわゆる「釉薬屋」です。釉薬屋にとって、主な取引相手は窯元。それも大量生産を目指す窯元たちです。
「釉薬にはたくさんの種類があります。技法も多く、あえて釉薬を縮れさせて焼き上げる梅花皮(かいらぎ)という古典製法など、美術品としてはものすごく価値のある焼きものもあります。しかし、それは日常使いの器とは別の嗜好品。産業として食器類を生産する波佐見では、器を“安定して作ること”が求められます。だから、わたしたちも安定した釉薬を窯元さんたちに供給するのが一番の仕事。少し大げさかもしれないけれど、それが使命だと思っています」。そのように話すのは、代表取締役社長の山脇秀行さん。

ここで釉薬を調合できるのは、山脇さんを含めて5人。全員が30年以上この仕事を続けているベテランばかりです。といっても、釉薬屋の仕事は、生地屋や型屋と違って、職人のようなイメージではまったくないと話します。
「どちらかというと、営業職に近いですね。釉薬の配達を兼ねて窯元に足を運び、問題があればすぐに対応します。今は“必要な分を必要な時に必要な分だけ”という時代。これが可能なのは、産地の強みのひとつでもありますね」。
釉薬の原料は石を粉末にしたもの。釉薬屋では、仕入れた原料(石の粉)を「湿式粉砕(しっしきふんさい)」という方法を使って水を加えながらさらに粉砕していきます。つまり、窯元に届けるときには液体になっており、灯油が入っている真っ赤なポリタンクで配達しています。元々は石ですから、生コンクリートの水分が多くなったような状態。つまり、大変な力仕事なのです。
焼き上がってみないとわからない。だからテストを重ねる
「1250度できれいに溶ける釉薬がほしい」「1300度で焼いたときに光沢がない釉薬はないだろうか」など、窯元の要望は実に様々。釉薬屋では、まずこのような要望を聞き、少しでも理想的な色合いになるように原料を調合し、配合を変えた「釉薬」を4〜5種類つくります。しかし、本番はここから。実際にその釉薬を使用する窯元でテストピースを焼いてもらうのです。それも、何度も何度も。
「焼き上がりを見て“Aはちょっと暗いね。CとDは明るいね。じゃあ、Bの配合をもうちょっと刻んで試してみようか”という風に段階的に決めていきます。もちろん、基本的な配合は経験上覚えていますし、たくさんの資料もありますが、大体は新しい色を要求されるもので、なかなか1発で求めている雰囲気を出せることはありません」。

焼きものの焼成方法は大きく分けてふたつ。燃料が完全燃焼するように十分に酸素がある状態で焼く「酸化焼成」と、酸素を与えずにどんどん温度を上げていく「還元焼成」です。釉薬は酸素の影響を受けるので、同じ釉薬を使ったとしても、窯元によって全く異なる発色になります。波佐見は、ほとんどが還元焼成ですが、それでも窯の温度はもちろん、窯の大きさ、商品の積み具合など、微妙な条件の違いだけで、発色に差は出てしまいます。条件が同じ窯はひとつとしてありません。
「お天気でも違うんですよ。気圧が高いと、煙突から煙が引っ張られて、ふだんの窯の状態とは変わりますよね。焼成時の条件が違ったのか、そもそも釉薬のブレなのか。この判断をするのがとても難しいので、同じ配合の釉薬を何度も焼成してテストを重ねるのです」。
ロングセラー商品と釉薬の関係
もっというと、同じ原料もひとつとしてありません。つまり、釉薬になる前・原料の段階でブレが生じている可能性もあるということ。自然物なので、ごく当たり前のことでもありますが、原料のブレを知っておくことも釉薬屋の重要な仕事。A、B、Cと異なる配合を用意し、新しい釉薬が出来上がった時点で、基準となる釉薬と比較。ここでもテストを重ねます。中には、随分と発色が異なるものも出てくるので、その場合は原料の配合を0.1%刻みで調整し、釉薬のブレを最小にするそうです。

「窯元さんのリクエストで日々、新しい色を試す一方で、20年間、ずっと同じ商品のために釉薬を調合することもあるんですよ。その場合は、20年前の釉薬で焼いたテストピース、直前の商品、今回調合した釉薬のテストピースの3つを見比べます」。 ロングセラー商品の場合、原料の産地の状況にも影響を受けます。例えば、外国の鉱山では、鉱石がとれなくなってしまうことも。
「中国が莫大な原料を使うようになり、それまで30年は大丈夫だと思っていた山が10年で原料が尽きてしまったり。オーストラリアやドイツなど、世界中に似たような石はあるのですが、やはり微妙に違いますよね。名称が同じでも、中身が変わって納品されることもあるくらいですから。未来永劫ではない原料を使いながら、20年前と同じものを作らなくちゃいけない。だからこそ、テストを重ねて微調整をしていくしかないんですね」。

釉薬の魅力。それは答えがありそうで、ないところ
「釉薬は料理と似てるんです。同じレシピを見てつくっても、ちょっとした調理方法で味が変わるじゃないですか。だからこそ、“これを30%入れて、これを35%入れた時には、どんな風に変わるのかな?”とか、”これをちょっと足してみたらどんな色になるのかな?”とか、想像が膨らみます。答えがありそうでないことが面白いんですよね!」
釉薬に限らず、焼きものづくりの楽しみはこの試行錯誤にあるのではないかと話す山脇さん。天然の資源だからこそ、機械で作る部品のように寸分たがわぬというわけにはいきません。その時々の“ブレ幅”を「実際に焼いて確かめる」という方法で確実に安定させること。ここには、人間の熱意と知恵、経験が間違いなく必要なのです。
波佐見焼の発展を担う、釉薬の研究員
次に訪れたのは、長崎県窯業技術センター。長崎県の試験研究機関として、陶磁器はもちろん、セラミックス全般の研究をしている施設です。ここには、釉薬の可能性を探るべく、日々、試行錯誤を重ねている研究員がいます。
釉薬のベースは、主に長石・カオリン・石英という鉱物。この3種類の成分の割合によって、いろいろな釉薬ができ上がるのはご存知でしょうか? 「これらの成分をコントロールすることで、焼きものの表情に変化を付けるんですよ」と教えてくれたのは、工学博士の吉田英樹さん。陶磁器科の科長です。

陶磁器科の大きな仕事のひとつは『釉薬データベース』を作成すること。これまでの研究結果だけでなく、研修生が実際に行った実験のサンプルなどもすべて残してもらっているそう。現在では、約46,000の釉薬データがあるといいます。
「もちろん、実際に使える釉薬というと、さらに絞られてきます。でも、それぞれ実験した時の細かい条件についても記載されているので、間違いなく指標にはなります。これを見ることで、ゼロからスタートするのではなく、最もベストな出発点がわかるんですね」

ベースはガラス。色の素は金属酸化物
「釉薬のベースは、ガラスなんです。ガラスは不純物が入ることで色が着きます。イメージしやすいのはステンドガラスでしょうか。まさにガラスの世界と釉薬の考え方はほぼ一緒なんですよね」。
釉薬は大まかに分けると、2種類。釉薬のベースに金属酸化物を加えたものと、釉薬のベースに顔料を加えたもの。イメージとしては、水(透明な釉薬のベース)に絵の具(金属酸化物または顔料)を混ぜるようなイメージです。着色するための成分をちょっとだけ加えるのです。
「金属酸化物入りの釉薬をかけた焼きものは、透明感のある仕上がり。透き通っていながらも、着色されています。一方、顔料入りの釉薬は、ペンキのようなイメージ。色そのものが前面に出た焼きものが仕上がります」。

染付をした(=絵を描いた)焼きものの場合は、顔料入りの釉薬では絵柄が隠れてしまうので、金属酸化物入りの釉薬をかけてしっかりと染付が見えるようにします。パキッとしたカラフルな色が特徴の器の場合、顔料入りの釉薬をセレクト。釉薬のかけ方もあるので、一概には言えませんが、このように2種類を使い分けていくそうです。
「例えば、さきほど絵の具という例えを出しましたが、実際には釉薬に絵の具で着色することはできません。なぜなら、釉薬は1300度の高温で焼かないと、ガラス質にならないからです。もしも、絵の具を1300度で焼いちゃったら、燃えてなくなっちゃうんですね。この温度に耐えられ、かつ着色能力がある成分が金属酸化物と顔料だったのです」。

呉須の正体はコバルト。焼きものは自然現象と技術の掛け合わせ
歴史的に古くからあるのは、金属酸化物入りの釉薬。その後、金属酸化物を色みの素としながら化学的に作られた顔料が登場します。“呉須(ごす)”は、金属酸化物の「コバルト」を加えたものですが、コバルトブルーとよく言われるように鮮やかな色が人気です。
「安定して色が出せるのは、コバルトの特徴なんですよ。条件を変えても、だいたいコバルトブルーと呼ばれるきれいな色になりますね。実は酸化鉄でも、似たようなことはできるんですけど、どうしてもきれいな色にならないんです。鉄は、焼く時の条件がちょっと変わっただけでも、色が安定しないのです。焼きものは、自然現象と技術をうまく掛け合わせることで作られているんですよね」。

「コバルトは磁石に使われる成分なので、電気自動車のモーターなど、今、大変需要があるんです。そのため、世界的にものすごく価格が上がってきています。このまま高騰することも考えられるので、違う原料をどういう風に釉薬として取り込めるかを考えるのも非常に大事。時代の移り変わりに合わせ、焼きもの文化を守るために新しい釉薬を開発するのも研究のひとつなんですよね」。
「ちなみに質感をマットにしたい場合は、釉薬のベースを変えます。釉薬はガラスといいましたが、わざとガラスの結晶を出してみたり、釉薬自体があまり溶けないような配合にしたり、表現を増やすのです。ガラスの場合は、透明であることを前提としてものを作らないといけないですが、釉薬は自由。透明なことは透明なのですが、最終的に透明じゃなくなる使い方をしても成立する。釉薬の奥深いところはここにありますね!」。
最近は、波佐見でも「土もの(陶器)」の人気が高まっています。これまで「石もの(磁器)」で使っていた釉薬をそのまま土もの(陶器)にかけても、生地の膨張率の違いからヒビが入ってしまうそう。この場合も、釉薬のベースを調整して対応するといいます。

目に見える色を科学的に研究する
金属酸化物が生み出す色と違って、顔料は人工的なものだからこそ、色さえ作ることができれば、可能性は無限に広がります。
「顔料の特徴は、粒がそのまま残っていること。人の目には、その粒が見えないので、全体の色として見えています。これが顔料の着色方法。金属酸化物の場合は、釉薬そのものに色が溶け込んでいるのです。自然のものだからこそ、ひとつになれるんでしょうね」。


釉薬のトレンド。機能性を追い求めて
釉薬の色は、常に流行を追いかけています。最近では、くすんだ色みが人気のため、鮮やかな顔料を使いながら、最終的にわざとくすませて仕上げることもあるそうです。また、器と車のカラーバリエーションはリンクする部分が多いといいます。
「今、注目しているのは、機能性。例えば、釉薬の選び方ひとつで皿に汚れが残らないようにできたり、フォーク跡が付きにくくしたり、機能性も追求できるんです。表面を平滑にする、わざと凹凸をつけるなど、たくさんの試みができるわけですね。これからの波佐見焼は、見た目だけでなく、機能性という面で付加価値を付けていきたいですね。そのために釉薬ができることを考えていきたいと思っています」。

【取材協力】
●窯研株式会社 https://yaeshima.co.jp/
●長崎県窯業技術センター https://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/
1階の展示スペースでは、窯業技術センターで行われた試作品を始め、産地の製品などを展示。HPでは、焼きものの基礎知識などの資料も公開しています。
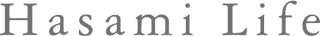
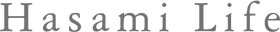
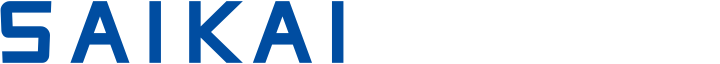
コメントを残す