
窯元探訪【筒山太一窯】福田太一さん vol.19 ふたつの窯を操る2代目に聞く、育てる波佐見焼・白化粧と御本の魅力。
波佐見町には全部で59軒の窯元があります。そして小さな町の至るところに、波佐見焼と真摯に向き合う「人」が存在します。 今回は、筒山太一窯(つつやたいちがま)の2代目・福田太一(ふくだ たいち)さんを訪ねました。 器づくりについてはもちろん、ふだんは見られないプライベートな顔まで、前編と後編に分けてお届けします。
使えばわかる波佐見焼、愛される白化粧。
“日用品としての器” で人気の高い波佐見焼。原料の多くは、天草陶石といわれる『石』なので、とにかくかたくて丈夫! 石もの(=磁器)と呼ばれ、見た目は艶やかで汚れがつきにくく、食器洗浄機OKと謳う食器が多いのも、なにかと忙しい現代人にとっては大きな魅力です。
その一方、波佐見町内でも土から生まれる土もの(=陶器)をメインに作陶を続ける窯元もあります。磁器とはひと味もふた味も違う陶器の魅力とは? 今回、訪ねたのはHasami Lifeでも大人気の陶器 『白化粧』シリーズを生み出す筒山太一窯(つつやたいちがま)さんです。

白化粧に使われている技法は、焼きもの業界では一般的に “粉引(こひき)”と呼ばれます。まるで粉を引いた(=まとった)ように美しい白い器に仕上がることからネーミングされたといわれており、もともとは朝鮮半島の伝統的な技法だといいます。
白化粧が一体、どんな風に作られているのか、さっそく筒山太一窯の小樽工場へ。小樽(おたる)ではなく(こだる)と読み、小樽郷(こだるごう)という地域にあります。お話を伺ったのは、筒山太一窯2代目・福田太一さん。


福田 太一(ふくだ たいち)
高校卒業後、長崎市内の調理師専門学校へ。料理を学んでから波佐見へ戻り、窯元の仕事に従事。2019年に父・福田友和さんの後を継ぎ、2代目に。焼きもののデザインから実際の作陶、経営まで担当する。趣味は釣り。
「白化粧はうちの大定番ですね。お客さまの反応もとてもよく、“使ってみてよかったから” と毎年、陶器まつりにやってきては、少しずつ買い足してくれる方もいるんですよ」
筒山太一窯の人気商品のひとつ、白化粧。化粧土と呼ばれる白い泥をかけて仕上げます。
「土で形を作ってから素焼きをします。そして、化粧土をかけてもう一度、素焼き。ここで化粧土を土にしっかり焼き付けないと、色がはげてしまうんですよ。最後に 釉薬(ゆうやく・うわぐすり)をかけて焼きしめます。作家さんが粉引をするときは、土が乾く前に化粧土をかけて1回の素焼きで仕上げることもあるようですが、わたしたちは2度の素焼きをします。うちで作っているほかの焼きものと比べても、確かに手間はかかっていますね」
「これが白化粧の素ですよ!」と見せてくれた化粧土は、まさに白い泥。化粧土はそれぞれの窯元が調合して使用しているそうです。オリジナルのレシピこそ、器の表情を決めるキモになるのです。
「うちのは粒子が粗いんです。白化粧のざらりとした独特な質感は、この化粧土によるものです。あとは釉薬をどうかけるか、も重要。薄くかければ、よりザラッとした質感が際立ち、厚くかければ、なめらかな仕上がりに。作家さんが作るものもまたきれいなんですよね。ひとつひとつのバランスが異なれば、また別の味わいが生まれる。それが粉引のいいところだと思っています」
焼きものの多くは、素焼き(素地)の上に絵付けなどを施し、釉薬をかけて仕上げます。ですから、器の印象を直接的に決めるのは、釉薬の色。ただし、白化粧は透明の釉薬を使っているので、化粧土の自然な “白” が活きています。
「見た目は真っ白い焼きものですが、ベースになっているのは赤い土です。こうして物になったときには表に出ない土の色ですが、土の色が変わるとまたガラッと表情が変わるのでおもしろいなと思います。化粧土とのバランスが最もいいのは、黒い土でもなく、肌色の土でもなく、赤い土なんですよね」

もしも、断面を見ることができたらなら、赤土、化粧土、透明釉の3層構造。化粧土でしっかりと粧(めか)しこむ技法ながらも「素地がどんなものでもいいわけではない」という太一さんの話は、わたしたち人間の世界にも通じることがあるような気がします。
焼きものの顔は、最終的に窯(かま)が決める。
筒山太一窯は、焼きものの町・波佐見の中でも特に窯元の多い中尾山にも、もうひとつの工場があります。1988年に中尾山で窯開きをし、第二工場として小樽工場ができたのは1996年。
「ここ(小樽工場)には還元焼成の窯、中尾山工場には酸化焼成の窯があり、ふたつの窯を使い分けています。温度管理は自動と手動の2種類ですが、仕上がりへの影響はほとんどありません。でも、還元焼成と酸化焼成では、同じ焼きものでもまったく違う仕上がりになるんですよ」

還元焼成:酸素が乏しい状態で焼き上げる方法。900~980℃に達したら、不全燃焼状態にする。
酸化焼成:酸素が十分に供給された状態で焼き上げる方法。1250℃まで温度を上げ、完全燃焼させる。
例えば、この2種類の陶器、どちらも筒山太一窯で焼かれていますが、単純なる色違いではありません。

「もちろん、釉薬も異なるのですが、ネイビーは還元焼成、パープルは酸化焼成で焼いているんですね。というのも酸化焼成にすると、釉薬の色がきれいに出るんですよ。ネイビーは透明に近い釉薬を使っており、色への影響が少ないため、還元焼成で焼きます。磁器は酸化焼成で焼くと、強度が弱くなってしまうのですが、陶器はどちらの方法でも強度はそこまで変わらないんです」
磁器を扱う窯元が多い波佐見では、還元焼成の窯が多いとか。同じ釉薬でも、窯によってまったく違う色が出るというから、焼きものは本当に奥が深い。取材の最中、ちょうど “窯詰め” が行われていました。釉薬をかけたあと、乾燥させた焼きものをいよいよ窯へ入れるという作業です。

整理整頓されて美しく積み上げられた焼きものを見ると、この技術もまた職人技であると気づかされます。上下左右、ギリギリまで積み重ねる様子に驚いていると、ある棒を見せてくれました。この高さまでは積んでもよい、という “目安棒” だそうです。

「窯の違いだけでなく、窯詰めされた位置によっても、焼きものの仕上がりが変わってしまうんですよ」と太一さん。窯をどう操るか、この話はもう少し続きます。
御本は生きている器、育てる波佐見焼。
窯の中で模様をつける焼きものがあります。

焼きもの業界では、“御本手(ごほんで)” と呼ばれる技法を使っているこの器は、特定の成分を含む陶土を還元焼成することで断片的に淡い斑点を生み出しています。安土桃山から江戸の初期、日本から “お手本” を朝鮮へ送って焼かせたとされる高麗茶碗からきているそうです。
1000℃以上になる窯の中ですから、もはや人の手仕事が及ぶ範囲ではありません。窯の中で生じる物質の変化によって仕上げるこの器は、まさに“窯頼み”。
「淡い斑点は、冷却するときにできるんですね。窯で焼くことで釉薬が溶けていきますが、そこに空いている小さな小さな穴に酸素が入り込むことによって、まあるく広がるように模様ができるのです」
つまり、御本を作るためには、とりわけ窯の温度管理と酸素濃度のバランスが重要ということ。

「ちょっとしたことで仕上がりに差が出てしまうので、これまであまり作っていなかったんですね。とにかく難しいんです。本来であれば、多少グレーっぽくなっても個体差のうち、魅力のひとつとして認められます。作家さんの作品だと余計にそうです。でも、うちみたいに均一な商品が求められる場合、どうしてもきれいに上がった焼きものと比べられてしまう。一定のものが上がらない状態を避けたいと思うと、大量には作れないんですよ」
水にくぐらせると、模様が変わる。それは酸素も入り込むような小さな穴が空いているから。洗ってそのままにしておくと、汚れが定着してしまうので、黒ずんでしまうこともあるそうです。
「水がしみてくるんだけど、どうなってるの?という問い合わせも、実際にありますね。そういうときは、米のとぎ汁につけると、穴をふさいでくれるので水の浸透を防げます。手入れが必要な分、使えば使うほど、味わいが変わっていきます。御本だけでなく、白化粧も同じですよ」

個体差もあれば、多少のお手入れも求められる。自然にゆだねるように生まれ、まるで生きているように育つ陶器の波佐見焼と、確かな匠の技を生かして均一に仕上げる磁器の波佐見焼とは、まさに真逆ともいえる魅力を持っています。
「御本を安定して生産できるように求められているので、以前より数多く作れるように工夫を重ね、テストを繰り返しています。陶器の波佐見焼を楽しみたい! という人が増えているんだなと思うとうれしいですもんね」



土、水、酸素、火。天気や湿度も含め、最後は自然の力に任せる。窯への積み方、釉薬の調整など、日々最善を尽くして焼きものを作り続ける太一さん。後編では、太一さんが考える料理と器の関係について伺います。
【筒山太一窯】
長崎県東彼杵郡波佐見町中尾郷1018
0956-85-4912
公式サイト https://taichigama.com/index.html
オンラインショップ https://taichigama.shop/
Instagram https://www.instagram.com/taichi_gama/
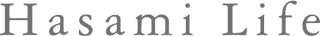
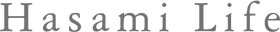
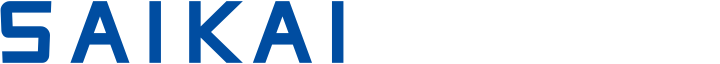
コメントを残す