
窯元探訪【利左ェ門窯】武村博昭さん vol.9 魔法のような職人たちの手仕事
波佐見町には全部で59つの窯元があります。そして小さな町の至るところに、波佐見焼と真摯に向き合う「人」が存在します。このシリーズでは、窯元を順番に尋ね、器づくりについてはもちろん、ふだんは見られないプライベートな顔までをご紹介します。
※記事内で紹介する商品の中には、Hasami Lifeで取り扱いのないものもございます。利左ェ門窯さんのオンラインストア等も併せてご確認ください。
磁器(石もの)をつくる窯元が多い波佐見町で、陶器(土もの)を手がけている「利左ェ門窯(りざえもん)窯」さん。分業制ではなく自社で生地づくりから一貫生産を行う、町内では珍しい窯元でもあります。
窯元探訪【利左ェ門窯】武村博昭さんへのインタビューの最終回は、博昭さんが大好きな"チーム利左ェ門"のメンバーの仕事ぶりを順番に紹介していきます。

水ごてで、ベストな厚みに成形。
最初に博昭さんに見せていただいたのは「水ごて」。

石膏の外型に陶土を入れて回転させながらヘラを押し当て、器の生地を成形します。水をさすことで表面をなめらかに仕上げることから「水ごて」と言うんですって。
博昭さんいわく「この"水ごて"は、経験と目と、指の感覚が頼り。厚みも自分たちで調整するんです。自分のヘラは自分で削って使うし、成形の仕方は人それぞれ違います。みんな同じやり方じゃなくていいんです。だって、一人ひとり生まれ持った手が違うんだから」とのこと。
手が違うと、やり方が違う。それぞれの職人さんが自分の技を磨き、それぞれの方法で美しく成形する。惚れ惚れとしてしまいます。
この作業をされた職人のひとりが三枝広樹(みえだ ひろき)さん。まるで簡単そうに、土をちぎっては型に入れて、ヘラを押し当て、手早くちょうどいい厚さに成形していきます。ですが、ある程度「水ごて」ができるようになるまでには、5年はかかるのだとか。職人技です。

三枝さんの実力を、博昭さんはこんな風に評しました。
「彼はね、なんでもできちゃう男です。絵付もできるし器用。また絵付が繊細なんです。な〜んか独特で基本からは外れてるんだけど、完璧に仕上げてくる。ヘラのにぎり方も私とは正反対なんだけど、これがうまい」
チームプレーの釉薬がけ
釉薬をかけていくのは、松山眞一(まつやま しんいち)さん。専用のはさみで挟んで、一枚ずつ釉薬にくぐらせていきます。

「松山くんもいろいろできるんです。釉薬かけ、窯積み、圧力鋳込み(いこみ)とか。松山くんはね、上手よ」
誇らしげに話す博昭さん、にこにこしていました。

取材時に扱っていた釉薬はムラになりやすい難しい性質のものだそうで、普段は絵付をされてる方も動員して、一斉に作業していました。流れるような共同作業は、まさにチームプレー。
松山さんが上手に釉薬をかけても、ハサミで挟んだ部分に釉薬がかからないため、どうしても小さな点ができます。よく見なければ気づかないほど小さな点。その部分を消すために、ほかの職人さんたちが細かく筆で釉薬を重ねていくのです。とても手が込んでいます。

マッハの刷毛目
お碗に化粧土を塗る「刷毛目(はけめ)」という作業をしていたのが、松田ひとみさん。博昭さんは彼女の仕事ぶりをひと言で「マッハ」と表現しました。
「ろくろの回転数は自分で調節できるんだけど、松田さんは一番回転数を多くしてて速いの! だからマッハ。刷毛目させたら速いですよ〜! あと彼女はしゃべるのも早口(笑)」

松田さんは以前勤めていた窯元で機械化が進んだため、手仕事が多い利左ェ門窯で働くことになったのだそう。
どんなときが楽しいですかと聞くと、松田さんは恥ずかしそうに「楽しいって、なか〜。いいものができたら、うれしいけど」と笑っていました。博昭さんも苦笑い。
「やっぱり、きついし大変な仕事ですよ。絵付は集中力がいる。笑いながらなんてできない。み〜んな真剣な顔してます」
自らも職人である博昭さんの言葉に、松田さんもうなずいていました。
松田さんが高速で行っていた「刷毛目」。こうして荒土が塗ることで、あえてビンテージっぽい質感にしているのだそうです。そしてこのお碗を素焼きしたあとに、今度は別の職人さんが絵付をしていきます。

濃筆(だみふで)で生まれる
繊細なグラデーション
絵付の技を見せてくださったのは水田豊子(みずた とよこ)さん。博昭さんが茶目っ気たっぷりに話しかけます。
「水田さんはうちに来る前から、今はない窯元さんでずーっと絵付をやってて……あれ?もう職人歴50年くらい? それとも60年?(笑)」
「もう!(笑)そんなに歳とってません! 絵付は波佐見に嫁いできてからです!」
「そうそう、長崎県内の諫早から嫁いできたんだよね」
そんな会話のあと、濃筆(だみふで)での絵付を見せてもらいました。


器を乗せたろくろを自分の好みの速さで回しながら、筆を器にふれさせます。グラデーションにする秘密は、筆に水を含ませること。呉須(ごす)と呼ばれる青い釉薬を筆全体に含ませたら、筆の先端にだけ水をつけるのです。この水が最初に器にふれます。それから徐々に筆の力加減と位置を変えることで、グラデーションを生み出すのです。
松田さんが塗った荒土のビンテージ感と、西野さんの絵付によるグラデーションが相まって美しい絵付。しかも呉須の中でも質の高い古代呉須を使用しているそう。素朴でシンプルながら手間暇がかかった制作工程を見せてもらいました。
10年ぶりの特殊な加工も、手が覚えてる。
見学させてくださいとお願いすると、「はい、どうぞ。これからポッチをつけますよ」と立山さん。まるで服にボタンがついてるような、立体的な飾りを器につけていきます。


立山さんのことも、博昭さんが紹介してくれます。
「立山さんもね、なんでもできる。几帳面な人でね、もう上手よ〜」
「利左ェ門窯では、なんでもしないといけないのよ(笑)」
「うっ、心が痛む……!」
「だから私、やせ細ってるやろ(笑)」
「働き者で、めっちゃ感謝してます!」
ふざけたやりとりの中に見える信頼関係。立山さん、このポッチをつける作業は10年ぶりとのことでした。「意外と手が覚えてるのよね」と気負った様子もなく丁寧に作業していきます。
博昭さんが、しみじみと話します。
「こういうポッチ付きの器は、昭和のころに人気で利左ェ門窯でつくってたんです。今だとレトロな感じがするねえ。最近ある料理屋さんが『同じ器をつくってほしい』と以前私たちがつくった実物を持ってきてお願いにきました。うちは職人が揃ってるし、できる限りそういう依頼も引き受けてます」
利左ェ門窯では、機械での大掛かりな作業をしないぶん、少ない個数や特殊な加工でも、柔軟に対応することができます。それは、腕の立つ職人さんの存在あってのこと。
今回すべての職人さんをご紹介することはできませんでしたが、16名の従業員と一緒に、今日も技の光る焼きものをつくりだしています。
"チーム利左ェ門"は、職人とともに。
熟練の職人だけが持つ魔法の手は、端正ながら温かみのある焼きものを生み出します。
ですが時代の流れとともに、波佐見焼でも機械が担う部分が多くなってきました。手作業だけでは一度につくる数に限りがあり、熟練度の差が生じる場合もあります。加えてどうしても多少は値段が張ってしまう。そうした理由から機械化を進める窯元も多くあるのです。
機械でつくられたものや、石もの(磁器)などの器も好きだと話す博昭さん。波佐見のいろんな窯元の話をして「あそこの窯元の焼きものもいいよね!」と教えてくれました。単純になにもかもを機械化するだけでなく、手作業をうまく組み合わせながら、分業制で産業として常に進化をしてきた波佐見焼の歴史を知っているからでしょう。

ただ、博昭さんたち兄弟がお父さまの代から目指してきたのは、一貫生産で独自性の強い陶器をつくること。波佐見には少ない陶器を極めて、手仕事のよさをしっかり残すこと。
数え切れないほどある波佐見焼の魅力の中で、特筆すべきは多様性ではないでしょうか。この土地では普段使いの器をメインに、どんなテイストのものでも貪欲につくってきました。磁器を分業制で量産する波佐見焼の中では少し異質な利左ェ門窯さんですが、手ごろな値段で新しい焼きものを生み出そうとする姿に、波佐見らしさを感じました。
利左ェ門窯さんがこの時代においても純度の高い手仕事を貫けたのは、きっと先代と職人さんたちへのリスペクトが強固だから。
取材の最中「利左ェ門窯さんは13代目の裕宣さんと、弟の博昭さんのおふたりを中心にこれまで……」とHasami Life 編集部が話すと、すかさず博昭さんは言いました。
「違う。中心は私たちではなく、職人さん。職人さんがいないと、利左ェ門はアウトなんです」
こうした思いがなければ、現在の利左ェ門窯さんは存在しないはず。
ずっと、職人さんとともに。"チーム利左ェ門"の戦う姿に、どうしてこれだけ魅力的な焼きものが生み出せるのか、その理由の一端を垣間見ることができました。

【利左ェ門窯】
長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷548-3
0956-85-4716
●公式サイト
http://www.rizaemon.jp/index.html
●オンラインストア
https://rizaemon.jp/shop/html/
https://www.instagram.com/rizaemongama/
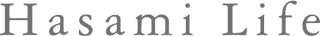
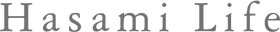
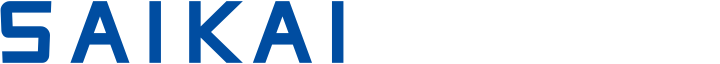
コメントを残す