
波佐見焼の話をしよう。【vol.1】デザインするひとたち
400年の伝統を持つ「やきものの町」として栄えてきた波佐見町。約14000人が暮らす小さな町では、現在、全国の一般家庭で使われる日用食器のなんと! 約13%もの量を生産しているといわれています。
窯業の仕事にたずさわっているのは約2000人。町へ出ると、あちこちに「波佐見焼のまわり」で働く人たちがいます。
このシリーズでは「波佐見焼をもっともっとおもしろくするために話をしよう」という趣旨のもと、会社の垣根を越え『同業者』のみなさんにお集まりいただいてざっくばらんにお話を伺います。

今回のテーマは「デザイン」。
波佐見では陶磁器をどうやってつくっているのか?
デザインする人たちは、どうやってこの仕事に就いたのか?
焼きものの仕事に興味がある方も必見です。
===お集まりいただいたみなさん===

(写真左から順に)
一誠陶器に入社して11年目。
池田希美(いけだ のぞみ)さん
Instagram
一龍陶苑に入社して18年目。
望月真希(もちづき まき)さん
Instagram
和山に入社して11年目。
林 恵深(はやし めぐみ)さん
Instagram
===================
デザイナーってどんな仕事?
――今日はお集まりいただき、ありがとうございます。ところでみなさん、面識はあるのでしょうか?
林さん(以下、林)
スウェーデン大使に納める波佐見焼をつくったとき、お会いしましたよね。銘板がなかったのですが、池田さんがすごくきれいに消しゴムハンコを彫ってくれて。
池田さん(以下、池田)
懐かしいですね! いつ頃でしょう? けっこう前ですよね?
望月さん(以下、望月)
みんなで集まれていたから、コロナ禍よりも前かな。あの機会は新鮮でしたね!
池田
スウェーデンのデザイナーさんがデザインしたものを、焼きものにどう落とし込むか? 波佐見全体で実現させる仕事だったので、各社「どれができるか?」という話し合いをするために集まって。それ以来、こうやって会うことはほぼありませんでした。
望月
改めまして、今日はよろしくお願いします。
林
よろしくお願いします。
同じ業種ですが、それぞれ会社での役割は少しずつ違うんだろうなと思っていたので、みなさんのお話を聞いてみたかったんですよね。だから、とてもうれしいです。
池田
わたしもです、よろしくお願いします。
そもそもの話になるのですが、今回「デザイナー」として呼んでいただきましたが、じつは自分からデザイナーと名乗るのはちょっとおこがましいような気持ちがありまして。

望月
同じです。少し恥ずかしいかも。
林
わかります。どちらかというと、わたしたちって「商業デザイナー」ですもんね。ゼロから生み出すというよりは、流行などを押さえながら、企画を提案していくような。
――「陶磁器デザイナー」という肩書きの方もいらっしゃいますが、そちらはいかがでしょうか?
池田
一般的にいえば、それが最もわかりやすいと思います。
望月
そうですね。わたしは肩書きを問われたら、「絵付・デザイン」や「商品開発」と伝えることが多いです。
池田
商品開発! 確かに一番しっくりくるかもしれないです。
林
うんうん。
望月
自分の中では「お悩み相談係」や「問題解決係」だと思っています。陶磁器に関して困っていること、求められていることをヒアリングして解決するのが仕事。
――つまり、今まで見たことのないような波佐見焼をデザインするというよりは、商社さんやお客さまが作りたいものを実現するためのデザイン?
一同
そうです、そうです。
林
波佐見には、独自の焼きものづくりを追求する作家さんも今はたくさんいますが、歴史的には「産業」として焼きものを作ってきた町。だから、量産できる商品のデザインを担当しているのがわたしたち。といっても、デザインだけをしているわけではなく、現場にも入るし、不具合が生じたら対策を練るし。
望月
どこで悪影響が出たのかを窯場からヒアリングし、陶土屋さんから生地屋さんまで、足を使って話を聞きに行ったりもしますよね。現場がスムーズに流れるような準備を全部しなくちゃ、という毎日です。
池田
うんうん。例えば「新商品を作ります」というときも、形を決め、デザイン決め、現場に落とし込んで流れるまでの雑務をすべて担当して。道具が必要であれば、それも準備して。
わたしたちは陶磁器まわりの「なんでも屋」かも?
――「デザイン」というと、華やかに聞こえますが、その作業は仕事のなかのひとつにすぎないのですね。
池田
本当にそうなんです。毎日ドロドロになって働いています。あっちで呼ばれ、こっちで呼ばれ、行ったり来たり、みたいな(笑)
一同
(笑)
――会社は違っても、同じような状況で働いているのがわかりました。それでは、実際にデザインに落とし込むときの話を伺いたいのですが、新しいデザインはどういうふうに考えていますか?
池田
わたしはアナログ人間なので、鉛筆や色鉛筆と紙を使います。使わない紙をクリップで止め、そこにアイディアをどんどんスケッチしていきます。
林
わたしは鉛筆と水彩絵の具ですね。パソコンは入社してから始めて、独学で一生懸命イラストレーターを覚えました。幾何学のようなカチッとした模様は、イラストレーターを使うこともあります。
望月
わたしは焼きものに直接、描いています。それが一番早くデザインできるから、すぐサンプルみたいなものを作ってしまいます。
林
すごくいいですね! わたしの父も「実物に近いものを見せるほうが、相手がわかりやすいからいいよ」とよく言っていました。そう考えると、間違いなく立体的なものがいいですもんね。
池田
なるほど!
もちろん、そのあとは型に起こして、量産体制にするんですよね?
=======
=======
望月
そうですね。この焼きものを仕上げるには何手間あるかな? と考えながら、まずはかけられる予算を聞いて。先方の意見と、わたしたちの意見を合わせて、現場に流れを確認して。
林
筆で描きにくいものは「ハンコ」にしようか、とかですよね。
望月
まさに。「パット印刷」でもいけるかも、「転写シート」を使おうか、などなど予算内で実現可能な方法を探っていきます。
――今日は実際、みなさんが手がけられた波佐見焼をお持ちいただきました。まずは一龍陶苑の望月さん、見せていただいてもよいでしょうか?
望月
なんだか恥ずかしいですね(笑)


ある日、社長夫人が中国の伝統的な刺繍・スワトウのハンカチを持ってきました。おばあさまの形見ということで「これを陶芸にしてもらうことはできる?」と。
まずはやってみようと、一度デザインしたのですが、刺繍のままだと釉薬かけるときに、盛り上がっているところが潰れてしまうんですね。何度も試行錯誤して、その都度、実現するためにデザインは変えたんですけど、そこに至るまでの気持ちは大事にしながら仕上げたのがこの「スワトウシリーズ」です。


色もたくさん試して、最初は真っ白から始まったんですが、ブルーやピンク、グレーなど、たくさん作りましたね。上品で大人っぽい焼きものをイメージしていて、安っぽい色にはしたくなかったので、ブルーにはグレーを入れたり。ピンクもサーモンピンクを調合しました。

こちらは釉薬のテスト焼きです。実際に焼いてみるのが一番わかりやすいので、すぐにこういうものを作って確認しちゃうんです。でも、手数が多すぎて、コストの面で商品化できていない焼きものもたくさんあります。これもそうですね。

林
おはじきみたいでかわいい!
池田
うんうん、とってもかわいい。
望月
すべてのデザインを商品化できるとは限りませんが、思い描いたものは実際に作ってみるようにしているんです。
――和山の林さんが持ってきてくださったのは?
林
「シャビーシックスタイル」というシリーズです。
アンティーク感を残したデザインで、軽くてザラザラしているのが特徴です。和山という会社なので「和」の心は残しつつ仕上げていますが、パスタなど洋食との相性がいいんですよ。



池田
これは釉薬を?
林
筆でまいています。
池田
一枚一枚、まいているんですね!
林
ザラザラした質感は好みが二分しますが、一度気に入ってくださったお客さまはリピートしてくれるシリーズです。リムを広めにしたのもポイント。リムにつけている模様はハンコでつけています。
―― 一誠陶器の池田さんはいかがでしょうか?
池田
わたしはテストを持参したので、直接メモが書きこまれていたりします。手描きでしか出せない風合いを大切にしているのが、うちの会社の特徴。特にうねうねとした呉須のラインを主役にした「チルダ」は、自分でもお気に入りのデザインです。描く人によって線の太さが変わることを想定して波打った線に決めたんです。個体差が個性になるように。


高台を作ることで立体的にかつ持ちやすくしているのもポイントです。特に「easy don」という丼は高台のまわりにカーブ状の溝をつけ、片手で持ちやすく熱さも感じにくくなっています。重ねて収納もできるんですよ。


――みなさんの波佐見焼が揃うと、当たり前ですが、三者三様ですね!
林
ほんとにおもしろいです。技術的にも聞きたいことがたくさんありますし。
望月
どうやって商品化していくのか、もっと詳しく聞きたくなってしまいますね。

どうして焼きものの世界に?
――ところでみなさん、どんな経緯で入社されたのですか?
池田
わたしは佐賀県立有田窯業大学校(以下、窯大)を卒業したあと、アパレルをはじめ、パン屋、雑貨屋など、モノを作るいろいろな業種で働いていました。今の会社の社長とは、歳こそ違うのですが、窯大の同級生だったので、ちょうどデザイナーを探しているタイミングで声をかけてもらいました。
実家は佐賀なのですが、生まれは埼玉。転勤族だったので大阪にも居たこともあり、今はふるさとに帰ってきたような感じです。
望月
わたしも窯大を卒業しています。宮崎出身ですが、子どもの頃は沖縄や北海道などに住んでいました。入社のきっかけというよりは、焼きものとの出会いの話になるのですが、わたしが中学2年生の時、父が出張のついでに「世界・炎の博覽会」というイベントへ立ち寄り、焼きものの作品をお土産として買って帰ってきて。
====
(メモ)
【世界・炎の博覽会】
1996年(平成8年)7月19日から同年10月13日まで開催された地方博覧会。正式名称は「ジャパンエキスポ佐賀'96 世界・焱の博覧会」。
佐賀県西松浦郡有田町および西有田町にまたがった有田会場をメインとして佐賀県内に3ヶ所の会場が設けられ、同県内外の九州北部の陶磁器にゆかりのある地域や集客が見込まれる施設に地域サテライト会場が設けられた。
====
そのとき、窯大の存在を知り、「焼きものの学校なんてあるんだね〜」と家族で話したのを覚えています。高校では、インテリア科に進んだのですが、授業の一環で陶芸コースがあり、初めてコーヒーカップを作ったら母がとても喜んでくれたんです。
当時は、焼きものを仕事にするつもりはまったくなく、作業療法士になろうかな?と考えていたのですが、あるとき、社会復帰のための土いじり体験を手伝ったとき、「やっぱり陶芸がしたいかも!」と気がついてしまい。高校卒業してから、窯大に入りました。ほとんどの方は2年間で卒業するのですが、わたしは不器用だったし、一からのスタートだったので、ひたすら筆で線を描いたり、土をこねつづけたり。

林
大学院みたいに延長できるんですよね。
望月
はい。窯大の生徒は、キャリアも年齢もさまざまでした。高卒もいれば、第二の人生の方もいて「焼きものが好き」という価値観は一緒という環境。わたしの代は1/3が地元のかた、2/3は県外のかたでしたね。わたし自身は窯大を卒業して一度、有田の窯元に就職したあと、ご縁があって今の会社に入りました。
林
わたしは実家が焼きものメーカーでしたが、自分はパティシエを目指していました。でも、父の体調が悪くなって現場を手伝うようになり、気がつけばデザインするようになっていました。なので、デザインの勉強はまったくしていなくて本当に独学です。
実家が廃業することが決まり、主力商品を今、在籍してる和山が引き継ぐことになりました。それでわたしにも一緒に来てくれ、と。当時は2〜3年いればいいかな? という気持ちでしたが、あっという間にもう11年(笑)。自力でデザインしながら、現場も入って、WEBサイトの立ち上げも担当し、本音をいえば「すべて中途半端なのかも」と悩んだ時期もありましたが、今は人に任せられることも増え、やっと自分のペースで働けるようになりました。
尊敬する先輩たちのデザイン
――波佐見にはたくさんの「デザインするひとたち」がいるので、今日はあえて同世代の女性というテーマを持ってお集まりいただきました。みなさんには、先輩のような存在はいらっしゃいますか?
池田
はい。わたしの先輩は、伝統工芸士「平安山 満広(へいあんざん みつひろ)」さんです。60代の男性でみんなからは「平安さん」と呼ばれています。一誠陶器の軸となるデザインは、すべて平安さんに引き継がれています。
弊社には「ZOE L'Atelier de Poterie」という新しいブランドができたのですが、このお店には昔ながらのテイストと新しい雑貨感覚の波佐見焼ラインを並べるため、平安さんと協力してデザイン開発をしました。その際、自分の得意なことで力を発揮することができたと思います。

――では、池田さんは平安さんから直接デザインを教わっているわけでないんですね。
池田
もちろん、大先輩なので技術的な相談は常にさせていただいていました。窯大を出たあと、焼きものの現場には入っていなかったのでわからないことばかりでしたし、当時は特に大変お世話になりました。ただ、平安さんから極力すべてを吸収しないように、引っ張られてテイストが似ないように、というのは意識していました。実際、部屋も離れていたので、教わるというよりは困った時に助けてもらう感じですね!
林
わたしの先輩も60代の男性です。松尾さんというかたで、和山のブランドの中でも人気のある、とてもメルヘンチックでかわいい「メリーゴーランド」シリーズや、花や植物があしらわれたノスタルジックな「フラワーパレード」シリーズを担当されているんですよ。
一方でわたしは無地をベースにするような、どちらかというと無骨なデザインを好んで作っています。
池田
女性だからかわいい焼きものを作る、というわけではもちろんないですよね。繊細な絵が描ける男性もたくさんいます。まさに平安さんも、かわいらしい花などのあしらいがとても上手。
望月
わたしの大好きな先輩も男性で今、70代の松井さん。商社さんから依頼されたウサギの柄とか、ネコの柄とか、自分が描く絵よりもずっとずっとかわいく仕上げますね。
男性が描くもののほうがなんとなく優しいようには感じてしまいます。「かわいい」って感覚が少し違うのかな?
林
うんうん。単純に男女という差ではないと思いつつ、男性が描くと、幅広く受けるタッチにでき上がるような気はします。

池田
すごくわかる。積み重ねたキャリアの影響も大きいですよね。
望月
松井さんは頭がやわらかいというか、年齢を重ねても感覚が若いから、話していても違和感がなくて。すべてが「いい塩梅」って感じでした。退社されてしまったあとも交流を続けていて、今でも憧れの人です。
――現場の職人さんたちとも日々、コミュニケーションをとるポジションだと思うのですが、現場の意見から生まれた商品はありますか? 例えば「こういう焼きものが作りたい」とか「あんな絵付がしてみたい」など。
林
それは意外とないかも?
池田
ZOE L'Atelier de Poterieの立ち上げの時、社長から「絵付の基礎ができてる人たちに一度デザインを描いてもらおう」という提案があって。形状は一緒で現場のみなさんに絵付してもらい、それらを全部並べて「どれがいいか?」を匿名でピックアップし、商品化したことがあります。
林
へ〜! おもしろい!
池田
人気のある「平碗」シリーズ なのですが、実際に今も販売されているんですよ。
現場から声が上がったというよりは、現場のモチベーションを高めるための試みでした。商社さんからの評判もよく、形状を変えて絵付してほしい、という依頼も増えました。いいことですよね、皆さんの自信や誇りにもつながると思うので!
「オリジナル」をつくるために。
――まず依頼があって、それに応えていく仕事だとは思いますが、自社ブランドのデザインを考える場合、大事にしていることはありますか?
池田
「面白い」とか、「ユニーク」とか、そういう要素が入っているデザインを意識しています。「かわいい」と一言でいっても、グラデーションがありますよね。その「かわいい」の中でも「ちょっと面白いね」が入っているデザインが個人的に大好きなんです。
商社さんからのご依頼のときでも、ここに共感してくださる担当者さんのときは、自分のアイデアと相手のアイデアを重ね、共通する部分を軸に考えます。面白いね、って言ってもらえると、やっぱりうれしいです。
林
わたしは建築やインテリアからヒントを得ることが多いかもしれません。家具屋さんにもよく足を運びます。特に照明にはものすごく惹かれますね。キラキラしている台形の模様をボウルの曲線の部分に落とし込んだら、どうなるだろう? と考えて作ったのがこの器。

ほかには、フランスの上品なスタイル「フレンチシック」をイメージしています。フランスには、黒っぽい土を使って釉薬で白さを出す不思議な食器があるんです。
――この数年でそれぞれの窯元さんの自社ブランドがとても豊かになっている印象を受けます。現場のみなさんとしてはなにか変化を感じていますか?
望月
そうですね。それはやっぱり「テーブルウェア・フェスティバル」がきっかけだと思います。
18年前、初めて東京ドームに出展したときは、全国の陶磁器が一堂に会する会場で「長崎の波佐見焼です」といっても、ほとんど相手にしてもらえなかったんですね。それまでは有田焼の大衆向けのラインを生産していたため、技術は持っているものの認知度がまったくない状態だったので。
そこで「波佐見というブランド力を上げていこう!」と、東京から先生を呼び、まずは自社ブランドを高めるため、各社指導を受けるようになりました。波佐見全体で上がっていこう、という試みがだんだんと形になってきたのかもしれません。

林
最近では、窯元併設のショップが増え、それぞれが独自でお披露目できているのもいい傾向です。
――自社ブランドはもちろん、それぞれの会社のオリジナル商品ですが、それ以外の波佐見焼は分業して作られていたりして、その相反する部分が並行して大切にされているのが本当に面白い町だなと思います。
望月
大量の注文が入ってきて、まかないきれないときは別の会社に助けてもらったりしますしね。
池田
焼きものを焼くスペースが足りないときは、ほかの窯元さんの窯の空いているところに入れてもらったりもするんですよ。
なんというか、とんでもない数の発注は「波佐見にきた注文」という感覚があります。
林
わかります。一社で対応しきれないときの協力体制が自然とできているような。各社、忙しさには波がありますし、手が空いているときは仕事が増えてありがたいな、ということも。お互いに助け合いながら……でも、経営者の視点はまた違うかも?(笑)
望月
確かにそうですね(笑)
池田
わたしたちは「現場の意見」だから(笑)
もちろん、助け合いはするんですけど、現場にいるデザイナーがいざ、ほかのメーカーさんに行って、別のデザイナーさんに相談することはなかなかないんですよね。だから、今日みたいに話ができる機会はとても貴重で楽しかったです。
林
社長同士が話してから、わたしたちのところに話が降りてくるのが普通ですもんね(笑)。
わたしもこうして話ができてうれしいです。
望月
同じような感覚で働いているんだな、というのに驚きましたし、「みなさんも頑張っているんだろうな」と思うと、励みになります。

取材後記
取材時間が2時間30分を過ぎ、まだまだおもしろい話が飛び出しそうな勢いと、和やかな雰囲気のなか、みなさんそれぞれの現場へ戻る時間に。「またどこかで話のつづきをしましょう」と帰っていきました。お忙しいなか、貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。
デザインする人たちも三者三様。三社による違いだって、もちろんあれど、波佐見焼への想いや情熱は同じ方向を向いているのだ、と実感するインタビューになりました。途中「波佐見全体で上がっていこう」という言葉がありましたが、こうして横のつながりが強くなっていくこともまたひとつの近道なのではないかと思うのです。
これからも Hasami Lifeは、「波佐見焼のまわり」で働くたくさんの人たちの声を聞き、「波佐見焼のいま」として記事に残していきたいと思います。
取材協力:
無添加で身体に優しいをコンセプトにしたベトナム料理フォーとカフェのお店
COYANE
https://www.instagram.com/hasami.coyane/
〒859-3701
長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2204-4
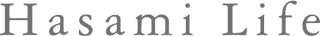
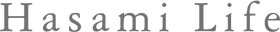






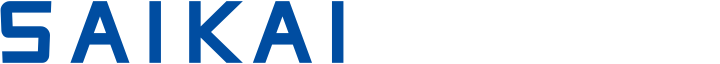
コメントを残す